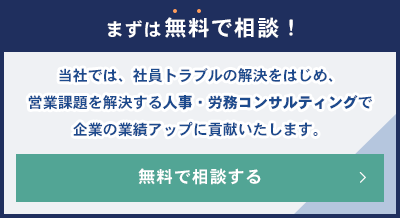会社の携帯電話を持つ社員の業務は、みなし労働?残業代の支払い義務がある?
最終更新日:2023.09.19
目次
「社用携帯を持っているから残業手当が欲しい」と社員が請求してきたら?
当社は営業社員に携帯電話を持たせています。
ある社員から「携帯電話を持っているのだからみなし労働ではなく、残業手当が欲しい」という請求がありました。どのように対応すればよいでしょうか。

「事業場外みなし労働時間制」の適用を受けていても、残業代が発生するケースがある
事業場外労働は、労働者が事業場外で労働する場合にあって、
労働時間の算定が困難なときに、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。
この「事業場外みなし労働時間制」が導入されている場合、所定の労働時間が8時間であれば、5時間しか働いていなくても、10時間働いても、8時間で計算されます。
「事業場外みなし労働時間制」の適用を受けるための要件は、
①労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で労働に従事したこと
②使用者が労働時間を算定しがたいこと
の大きく分けて2つです。
そのため上記の要件が満たされてないと、「事業場外みなし労働時間制」の適用を受けていても、残業代が発生するケースがあります。
社員の労働時間が把握・管理できる状態だと、みなし労働適用外
裁判例では、
営業社員について勤務時間を定めたり、携帯電話を支給したりしたことから
が、いずれも「事業場外みなし労働時間制」の適用を否定するにあたって、
会社が具体的に社員の労働時間を管理・把握していたことを認定しています。
具体的な労働時間の把握が可能なのは、下記の3点
行政通達(昭63・1・1基発1号)では、次のような場合は具体的な労働時間の把握が可能であるとされています。
①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰宅時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
「事業外みなし労働時間」に関する就業規則への記載は勿論ですが、労働契約書や労使協定を適切に締結し、
対象社員一人一人に周知する必要があります。
会社が労働時間を管理・把握してない場合の未払労働債務は、従業員の言い分が通る場合が多い
事業場の外で業務に従事する社員であっても、
には、「労働時間を算定し難い」という要件には該当せず、「事業場外みなし労働時間制」の適用は受けません。
しかしながら、「事業場外みなし労働時間制」の適用を受けていたとしても、所定の労働時間は8時間でも、実際働いた時間が10時間であった場合は、2時間分の残業代を支払わなければなりません。
また、会社が労働時間を管理・把握してない場合の時間外労働等における未払労働債務は、従業員の一方的な時間が通る場合が多いため、そのコストが莫大になる可能性があります。
労働時間や実施内容の管理の方法に十分注意してください。
人材マネジメント上のポイント
労働時間に関しては、法に従って厳格に対応することが求められますが、拘束性等がない場合においては、
ではないでしょうか。
その際の視点として、従業員の目線が内部ではなく、外部に向くようにする、
さらには、仕事における充実、その結果としての当事者意識等の醸成が求められます。
これらの価値観を浸透させるにおいて、人材マネジメント上の施策は様々あるかと思います。また、従業員の動向を日々、チェックすることが重要になります。それには、月並みかもしれませんが、管理者が従業員の動向を日々チェックすることが必要です。
例えば、業務の進捗、周りとのコミュニケーション状況などが挙げられます。
また、
することも重要になるかと思います。